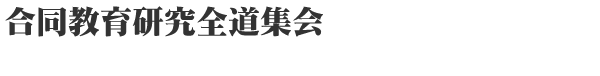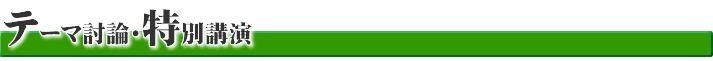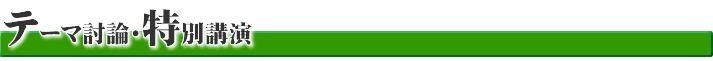
�e�[�}���_�@�P
���@�������鋳��ƎЉ�̎�����
�R�[�f�B�l�[�^�[
| �@ |
���{�@�@�O |
�i�����H�ƍ��Z�j |
�p�l���[
| |
�_�ہ@��n |
�i���R�@���c�j |
| |
�R�{�@���r |
�i�L�����Z�j |
| |
�k�C����w�w�� |
�@ |

|
�@�{�e�[�}���_�́A2013�N�Ă̎Q�c�@�I���ʼn������͂��c�Ȃ̑������߂鍑����J�����ĊJ�Â���܂����B�����Ɏ��O��R�₷���{�����Ƃ��̕⊮���͂ł����A���@�����ɂ��A�푈�ւ̓����J����A�����̎匠���N�����댯�����뜜���鍑�����_���l�����āA�����𐳖ʂ������Ɍf���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�������A���{�����@�̈Ӌ`���w�ђ����A���@�������鋳��ƎЉ�̎��������߂�^���Ɛ��_�����߂���g�݂��d�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�p�l���[�͖@���̐��ƂƂ��āA���ٌ�m�̐_�ۑ�n����A������H�҂Ƃ��āA���@�o�O���ƂőS�����삯����R�{���r����ɂ��肢���܂����B����ɁA��҂��猩�����@�ς�����Ă��炨���ƁA�k��ŎR�{����̍u�`����u���Ă��鋳���u�]�̑�w���ɂ��p�l���[�������Ă��������܂����B�R�[�f�B�l�[�^�[�͎�����L�x�Ȏ��Ǝ��H���s���Ă��鏼�{�O�����߂܂����B
�@�_�ەٌ�m�⍂�Z�̎Љ�ȋ����̎R�{���r����́A���@���ɊS�������ďW��ɎQ������l�����ł����Ă��A�u���@�Ƃ͉����v�u���@�͒N�̂��߂ɂ���̂��v�Ƃ��������{���u������`�v���u�m���Ă��Ȃ��v�u�������Ă��Ȃ������v���Ԃ����炩�ɂ���܂����B���@����������̂ł͂Ȃ��A���͎҂̖\����}����m���ߏ��n�ł���Ƃ������Ƃ��A�傫���L���邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��������܂����B
�@�k�吶�̃p�l���[�́A�����̎Ă��������U��Ԃ��āA���w�Z�E���Z�ƁA�u�̂��߂ɒm���Ƃ��ĈËL������e�Ƃ��Č��@���Ƃ炦��悤�ɂȂ��Ă��܂����v�Ǝw�E���܂����B����܂ł̊w�Z�ł̌��@�̎��Ƃɂ��āA���Ȃ������A�l����������w�E�ł����B�u�m���v�Ƃ��ċ������ނ̂ł͂Ȃ��A�����̐l���ƕ��a����錛�@�̈Ӌ`���w�ԋ�����H�����߂��Ă��܂��B
�@�Љ�ȋ������������@�����グ��̂ł͂Ȃ��A���ׂĂ̋��ȁA�����鋳�犈���̒��Ō��@����������������H���s�����Ƃ����߂��Ă��܂��B�����ς����s�����Ζ����Ԓ����ȂǁA����Ȑ���ł����̂��Ƌ��т����Ȃ�悤�Ȋw�Z�E�Љ�̏��L���钆�A�R�S���̎Q���҈�l��l���������ɂł��邱�Ƃ͉�����^���ɍl����W��ƂȂ�܂����B
�e�[�}���_�@�Q
�������͌����Ƃǂ�����������
�R�[�f�B�l�[�^�[
| �@ |
�쌴 �ΗY |
�i�D�y�Վ��H�ƍ��Z�j |
�p�l���[
| |
�r�c�@�l�i |
�i�ވ�]���ƍ��Z�j |
|
���ˁ@�@�� |
�i�t���[�p�[�\�i���e�B�j |
|
�n糁@���� |
�i�M�K�f�U�C����\�j |

|
�@���߂Ƀp�l���[�̎��˂���A�n糂���A�u�R�E�P�P�v�ɕ����ŋN�����A�ǂ�Ȏv���ŎD�y�ɔ����̂��ɂ��āA������܂����B
�@�S�R�Ń��W�I�̃p�[�\�i���e�B�[�����Ă������˂���́A�u�������������������A�����̒m�����قƂ�ǂȂ��A���͂����Ŏ��ʂȂƊ����Ȃ���A�P�O���ԁA�Q�S���Ԃ̃��W�I�����œ`���������v���ƁA�u�����̂��Ƃ͎����Ŏ�邱�ƂɋC�Â��A�P�Q���ɒP�g�ŎD�y�ւ̔������ӂ����v�o�܂����܂����B�u���O�Ɂu����v�Ə�������A�������o�b�V���O�ɂ����A�u����ł����邱�Ƃł����A�����̐������������Ȃ������B�����q�ǂ����Y�݂����Ƃ����v�������f�𑣂����v�Ɠ����̐S�����q�ׂ܂����B
�@�����s�ɏZ��ł����n糂���́A�u�S���W������w�Z�ĊJ�f�������Ƃ����B�}�X�N���Ƃ葤�a�̏������q�ǂ��������{���Ă��肢���B�w�Z����댯�ȏɂ��ĉ��̐������Ȃ��A�Z��̎g�p�ɂ��Ă��ی�҂ɃA���P�[�g���Ƃ茟�����Ă����B���ȏȂ̐����������A�q�ǂ����������p�����Ȃ��Ɗ����A�U���ɎD�y�ɔ����v�ƕ��܂����B�u�����ɂƂǂ܂����F�l���A�q�ǂ��Ԃŕ��f���N���ꂵ��ł������A����邵���Ȃ������v����������܂����B
�@���Z�Љ�ȋ����̒r�c����́A�u���ł����l�ƁA�ł��Ȃ������l�����邱�Ƃ����f�ƑΗ���ł���B�������̖͂��ɖڂ������A�s�M�ƑΗ�����ǂ�����ċ����̊W�������Ă������v�Ƃ̉ۑ肪��N����A�Q���҂��܂߂����_��ʂ��āA�u�q�ǂ������ɐ��m�Ȏ�����`���A�q�ǂ���������̓I�ɔ��f���s�����Ă����͂����Ă������Ɓv�A�u��l�ЂƂ�̎s�����A�Ȋw�I�m���������I���{�Ƃ��Ď��Ă�悤�ɂ��邱�Ɓv�̑�����m�F����܂����B
�e�[�}���_�@�R
�w�ԁ@�����@�Ȃ���@�`�u�����Â炳�v���z���ā`
�R�[�f�B�l�[�^�[
�p�l���[
| |
�n��@��j |
�i�D�y��ˍ��Z�j |
|
�D�y��ˍ��Z���t�y�� |
���k�EOB�EOG |

|
�@�Ƃ����u�ʓI�v�u�l��`�v�I�ɂȂ肪���Ȑi�H�̎w������A�u�w�Z�ł����o���Ȃ�"�Ȃ���"��"�A��"�̊w�т��ɂ������X�̎��H�v�̔����ց[�B���N�̃e�[�}���_�B�́A��N�Ƃ͎��ς��A�s������������Z���E���Ɛ���^�Ƀt���A�Ƃ̌𗬂��s���܂����B
�@
�e�[�}���_�̎n�܂�͎�҂̊�]�ƕs���A���ӂ����̂܂܉��F�ɂ����t���[�g�̉��t����ŁA�u�Q�X�g�v�Q���̓�ˍ��Z���t�y�����k�Ƃn�f�����ꂼ��ɁA�u�c�t�����@���߂����v�u���t�ƂƂ��Ă̖����͂��邾�낤���H�v�Ɓu���܁v�̎��������A�t���A�̎Q���҂Ƃ́u���������v�œ��_�������݂܂����B
�@�u�v���̉��t�҂��߂������Ɓv�����A�t���A�̍��Z��������́u���킵�������������邱�Ƃ͂��炵���v�Ɣ������[�B�u�w�Z�̎w���́A�Ƃ������"�͂�������"�ɌX�������v�u���i�A���сA�i�w���сA�A�E���\"�q�ǂ������̂���"�ɁA"����Ȃ�"�Ƃ���"�m����"�����߁A���k������"�͂����"���ɂ͂߂��߂Έ��S�B�����Ȃ��Ă����Ȃ����H�v�u�{���ɑ厖�Ȃ��͖̂ڂɌ����Ȃ����Ƃ������B���̂��Ƃ��A�F�l�Ƃ̂Ȃ���Ƃ��A�ڂɌ����Ȃ�����炪�A���͐��k�ɂƂ��ĉ�������B���������������������ꂽ�v�Ɣ���������܂����B�R�[�f�B�l�[�^�[�̏㌴�T�ꂳ��́u���`�����L�����A����́A�i���Љ�ւ̓K������҂����ɋ����A�ی��̂Ȃ������Ɓu�����n���v�ɔނ��ǂ�����Ă��͂��Ȃ����H�v�̖₢�����A�D�y���[�J�����j�I���쑺����̊���������A��҂̎����Ɓu�A�сi�Ȃ���j�v�A�w�Z�ƒn��Љ���l����e�[�}���_�ɂȂ�܂����B
�e�[�}���_�@�S
�u�����ƊǗ��v�����z������H�E�w�Z�Â���
�R�[�f�B�l�[�^�[
| �@ |
���� �N�W���� |
�i�����g�j |
�p�l���[
| |
�R�{�@�m�j |
�i�k���s�����w�Z�j |
|
�@���^ |
�i�����Ȓ����听���w�Z�j |
|
�����@�r�� |
�i�D�y�s�����S�k���w�Z�j |
�@�p�l���[�̎R�{����́A��ςȊw���Ȃ̂ł����A�Z�����d�_�Ɏ���v�����g�̊��p�A�V�ѐS��厖�ɂ��邽�߁A�Q�[���������ꂽ���Ɖ��P������܂����B�����āA�����̋��t�������̊w���ɂ�������Ă����悤�Ȏw���̐��ɂȂ�A�������������Ă���Ƙb����Ă��܂����B
�@����́A���T�Ƃ肭�E��ł̎��ƌ𗬂�ʂ��āu�������Ƃ��������v�Ƃ����肢���A�ъ�����w�Z�Â���̂Ƃ肭�݂��Љ��܂����B���̂Ƃ肭�݂ŐE���������邭�Ȃ�A�ی�҂ɂ��q�ǂ��̎p�i�����j�����Ă��炢�����Ƃ����b���ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@��������́A�q�ǂ������̍�i�����ėǂ��Ƃ����b��ɂ����Ƃ肭�݁A�x�e���������C�Ŏw���@�̍u�t�߂��Ƃ肭�݂ȂǁA�w���E�w�N�E�w�Z�S�̂ł̋��͋����������������܂����B
�@�@�u�q�ǂ�������O�ɂ��Ċ肤���ƁA�E��Ō��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ̃q���g������������炦���v�A�u���t�̂�����ߊ��̍L������̐��������Ă������ꂾ���A�w�ǂ����Ƃ��������x�w�q�ǂ��̐�������ԁx�Ƃ肭�݂��Č��C���o���v�A�u�����Ɛ[�߂����v�̊��z�����܂����B
�e�[�}���_�@�T
�k��"�A�C�k�l�����"���l����
�R�[�f�B�l�[�^�[
| �@ |
���� �T�� |
�i�k��J������������j |
��
| |
�����@��i |
�i�k�C���A�C�k����������j |
�@�e�[�}���_�̑O���́A��������A��������̕Ɋ�Â��A�Q���ґS���ŁA�k��u�A�C�k�l�����v�̗��j�I�w�i�A�⍜�ԊҌ��̌o�܂��m�F�������܂����B
�@�������ォ����ɂ����āA�k�C���E�����E�瓇�ɂ����āA�k����͂��߂Ƃ��鋌�鍑��w�𒆐S�Ƃ���l�ފw�E��U�w�̌����҂ɂ���ăA�C�k�l���̔��@�Ǝ��W���s���܂����B�u�w�p�����v�̖��̂��ƂŁA�g�D�I�Ɍ��R�ƌJ��Ԃ��ꂽ�A�C�k��n�́u���@�v�ŏW�߂�ꂽ�l���͂P�O�O�O�̂ɋy�т܂��B
�@�P�X�W�O�N��ɃE�^������i�����j���⍜�̕ԊҁE�ԗ�����߁A�k��\���Ɂu�A�C�k�l���[�����v����������܂������A���@���߂���o�܂�^���͍����Ɏ���܂Ŗ��炩�ɂ���Ă��炸�A���݁A�⍜�Ԋ҂�k��ɋ��߂�u�k��l�����Ɋւ���ٔ��v���W�����ł��B
�@�㔼�̓��_�ł́A�s�����ȑΉ��𑱂���k��̎p���𐳂��A�^�������A�⍜�̕ԊҁA�⑰�ւ̎Ӎ߂����߂Ă������ƂȂǁA����̉ۑ�ɂ��ĔF����[�߂܂����B���̖����u�����i�s����l�����v�ƂƂ炦�A�L���s���ɓ`���A�����Ǝx�����L���Ă������Ƃ̏d�v�����m�F����܂����B
|