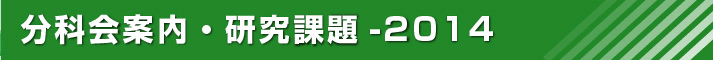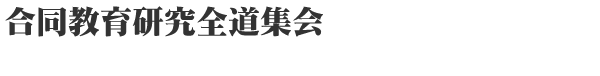
|
||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
第一分科会 国語教育
研究課題
| (1) 国語教育の現状と中心課題 | |
| ① 子どもの学力の実態と国語教育の現状 | |
| ② 改訂習指導要領・道徳教育の強制など教科書の問題点と教育課程づくり・自主教材の内容充実 | |
| ③ 研究の組織化と日常のとりくみ | |
| (2) 日本語教育―小・中・高の関連を明確にして | |
| ① 日本語の基礎(音声・文字・語彙・文法・漢字漢語教育など)をどう教えるか | |
| ② 子どもの日本語の学力問題 | |
| (3) 言語活動教育 | |
| ① 読み方教育・文学教育(文学的文章・現代文学・古典文学・説明的文学・評論教材)の内容と指導法 | |
| ② 作文・つづり方教育(韻文・小論文などを含む) | |
| ③ 自主教材の発掘・研究(憲法の教育・平和教育・北海道の文学) | |
| (4) 読み聞かせ・読書活動 | |
第二分科会 外国語教育
研究課題
| (1) 外国語教育の現状と課題 ― 生徒の学力の実態・外国語教育の現状と今後をとらえ、実践と研究を明らかにする | |
| ① 外国語教育の目的と全体構造を明らかにする | |
| ② 新学習指導要領の問題点を実践的・理論的に明らかにする | |
| ③ 評価方法と課題を明らかにする | |
| (2) 外国語教育の内容と方法 | |
| ① 言語体系(音声・文字・語彙・文法)の教育の内容と方法を明らかにする | |
| ② 言語活動(音声コミュニケーションと文字コミュニケーション)の教育内容と方法を明らかにする | |
| ③ 取り上げる材料の選定・掘り起こしを行い、その指導過程を明らかにする | |
第三分科会 社会科教育
研究課題
| (1) 社会科教育を取り巻く現状と課題 |
|
| ① 改訂学習指導要領と教科書検定・採択 |
|
| ② 東日本大震災と原発事故・放射能汚染が投げかける社会の諸問題 | |
| ③ 改憲と今問われる私たちの歴史認識 | |
| ④ 道徳教育の導入 | |
| (2) 子どもたちとともに考え、悩み、未来への希望をはぐくむ社会科教育をどのようにつくるかーその目的・内容・方法を探る | |
| ① 地域学習は何をめざすべきなのか、その可能性を探る |
|
| ② 過去の事実を正確に知り、平和な未来を希求するための社会科・歴史教育のありかた | |
| ③ 日本国憲法を学び、それを生かし、使う社会科・公民科教育とは | |
| ④ 北海道の子どもたちに必要な社会科・地歴科・公民科教育課程の編成のありかた -全体構造の模索- | |
第四分科会 数学教育
研究課題
| (1) 「数学は本当におもしろいんだなあ」という気持ちにさせるにはどうしたらよいか | |
| (2) 楽しみながら、数学の世界が見える教材にはどんなものがあるか | |
| (3) 子どもの学習意欲をもり上げる数学教育とはどんなものがあるか | |
第五分科会 理科教育
研究課題
| (1) 子どもが楽しみながら自然科学の基礎を着実に学ぶことができる授業をどのように創るか。 | |
| (2) 子どもと教師の意欲を引き出す、わくわく実験やものづくり教材をどのように開発するか。 | |
| (3) 「地域の自然」をどのように教材化するか。 | |
| (4) 「自然科学教育が育てる学力」を身につけることができる教育課程をどのようにつくるか。 | |
第六分科会 美術教育
研究課題
| (1) 子どもたちを取り巻く様々な状況・実態を明らかにし、美術教育によってどのような力を育ててゆくかを現場の実践を通して研究を深める | |
| (2) 子どもたちが楽しく主体的に制作や鑑賞を通して自己の感性を高め、作品づくりなどで達成感や心からの感動を味わうことができる教材や授業について研究する | |
| (3) 子どもたちの作品や鑑賞活動を通じ、美術が心身ともに健全な児童生徒を育成するために不可欠な科目であることを明らかにし、造形活動によって身に付く学力を確かめられる研究を推進する | |
第七分科会 書教育
研究課題
| (1) 正しく美しい文字を書きたい、思いや感情を込めた文字表現をしたい、自己の存在を何らかの形で確かめたいという子どもたちへの指導・援助のあり方を考える | |
| (2) 真の意味での「生きる力」を、書写・書教育を通じて習得できるようにするための教材・課題選びについて考える | |
| (3) 子どもたちをとりまく今日の社会や教育の現状を検討し、子どもたちの「育ち」にとって、書教育がもつ可能性について検討する | |
第八分科会 音楽教育
研究課題
| (1) 音楽教育の問題点とその解決の方向性を明らかにする | |
| (2) 生きいきとした音楽の授業はどうしたらつくれるのか、そのための教材、子どもの見方、目標の設定と評価、授業方法を実践的に解明していく | |
| (3) 主体的な全校音楽文化活動のあり方とその実践づくり | |
| (4) 子どもの成長発達に即した音楽教育の展望を明らかにする | |
第九分科会 技術・職業教育
研究課題
| (1) 技術・職業教育をめぐる状況 | |
| ① 生徒をとりまく状況(学習・生活・進路) | |
| ② 教育条件の整備と北海道の教育政策 | |
| ③ 学校間・地域との連携 | |
| ④ キャリア教育と技術・職業教育 | |
| (2) 教育実践と学校づくり | |
| ① 中学校の教育実践(技術科) | |
| ② 高校教育の教育実践(専門学科) | |
| ③ 職業教育・職業訓練と学力保障 | |
| ④ 学習指導要領の改訂と教育課程の編成 | |
第十分科会 家庭科教育
研究課題
| (1) 総合的に学ぶ家庭科で子どもが主体となる学びをどうつくるか | |
| ① 子どもの生活の現状をどうとらえるか | |
| ② 小・中・高の現状はどうなっているか | |
| ③ 家庭科における子ども主体の学びをどうつくるか | |
| (2) これからの家庭科教育 | |
| ① 学習指導要領・教科書と家庭科 | |
| ② 家庭科教育に関わる条件整備 | |
第十一分科会 保健・体育教育
《 学校保健分散会 》
| (1) 学校保健の実践的課題 | |
| ① 子どもの健康・発達を保障する健康診断をどう創造していくか | |
| ② 健康認識をどう育てるか | |
| ③ 様々な発達課題に向き合う子ども・青年の自立をどう援助するか | |
| ④ 自主的な保健委員会活動をどう育てるか | |
| ⑤ 民主的学校保健づくりと地域・父母との連携 | |
| (2) 学校保健の現状と課題 | |
| ① 子どもの健康・発達実態とその課題 | |
| ② 健康診断、予防接種、スクールカウセラー、特別支援教育のあり方、いじめ問題をめぐる状況の交流 | |
| ③ 脱ゆとり教育・学力偏重主義が子どもたちに与える影響と課題 | |
| ④ 学校保健をめぐる教育条件と養護教諭の権利問題の現状と課題 | |
| ⑤ 全校配置・複数配置運動前進のための取り組み | |
《 保健体育分散会 》
| (1) 教育課程の編成と改善・充実 | |
| (2) 保健体育の授業研究、実践の交流と今後の課題 | |
| ① 体育の授業実践の交流 | |
| ② 保健(性教育を含む)の授業実践の交流 | |
| (3) 体育的行事等の実践交流 | |
第十二分科会 総合学習・生活科
研究課題-総合的な学習の時間・生活科
| (1) 「総合」の授業づくりにおけるアプローチとその成果についての検討 | |
| ① 学習者の要求(学びたいこと)と教師の要求(学ばせたいこと)の統一にどうとりくんだのか | |
| ② 目標設定における知識・技能・情意の統一にどう取り組んだのか | |
| ③ 子どもにどのような力がついたのか、その検証はどのように行いうるのか | |
| (2) 「生活」の授業づくりにおけるアプローチとその成果についての検討 - 特に体験によって学ばれたことを、具体的に子どもの学習の成果から厳密に検証を図る | |
| (3) 総合・生活科と、学校づくりや教育課程との関係の在り方を探る | |
| (4) 総合・生活科と、施策の要求する「学力」と地域性との関係についての検討 | |
第十三分科会 教育課程と子どもの学力評価
研究課題
| (1) 子ども・生徒の学力と発達の現状、小中学校における「全国学力・学習状況調査」の影響 | |
| (2) 教育課程づくりのとりくみと課題 | |
| (3) すべての子ども・生徒に確かな学力と発達を保障する、わかる授業と総合学習 | |
| (4) 子ども・生徒の自治能力を育てる学級活動・部活動・生徒会活動など、それらを通じた学校づくり | |
| (5) 子ども達の発達を保障する評価 | |
| (6) 「道徳教育」押しつけの実態と、民主的人格をめざす道徳の実践 | |
第十四分科会 学校と家庭の生活指導
研究課題
| (1) 北海道の各地域に見られる子どもの生活状況 | |
| ① 発達に刻み込まれた『貧困』状況と発達要求を交流し、つかむ | |
| ② 『学力』問題、ゼロトレランスに揺れる学校で子どもたちはどうなっているのかを交流する | |
| (2) 安心できる場所づくりと自信を生み出す活動 | |
| ① 「学校」「教室」に安心できる居場所をどのようにつくり出したのか | |
| ② 発達要求にもとづいた自信を生み出す活動をどのようにつくり出したのか | |
| (3) 子どもの現実とひびき合う自治活動 | |
| ① 子どもと子ども、子どもと大人が語り合い、対話・討論・討議のなかでどのような合意をつくり出したのか | |
| ② 『遊び』や『学び』を通して、平和的で共感的な世界をどのようにつくりだしたのか | |
| (4) 子どもをまん中においた共同 | |
| ① 子育て・教育実践の悩みを語り合う関係づくり | |
| ② 子どもの発達を支援するネットワーク | |
第十五分科会 教育条件確立の運動
研究課題
| (1) 国と地方、地方自治体の教育予算の問題点と子ども・教育への影響 | |
| ① 義務教育費国庫負担金や就学援助費の削減、学校統廃合・学校現業職「委託化」・「道立学校支援室」設置とその影響、私学助成の抑制と実態など | |
| ② 貧困と格差」拡大が子ども・教育に及ぼす影響、「高校就学支援金制度」問題、給食費・教材費などの学校徴収金の実態など | |
| (2) 教育費無償化、ゆきとどいた教育を求める運動の進め方 | |
| ① 三十人以下学級の実現、教職員定数増と労働条件の改善 | |
| ② 子どもの学習権と地域の教育を守る運動 |
|
| ③ 子ども・青年の修学保障、私学助成の拡充など教育予算充実の運動 | |
第十六分科会 子ども、父母参加の学校づくり
研究課題
| (1) 子どもと学校、家族・家庭、地域の現状を、教育政策との関係を踏まえて、しっかりとつかむこと。 | |
| (2) 子ども、保護者と教職員、そして地域による学校づくりの実践交流をすること。 | |
| (3) 教職員集団の実態を踏まえ、同僚性を高め、教育的力量をどのように高めあうか。授業づくりや自治活動を中心としながら、 教育活動と民主的学校づくりを共同的・創造的にすすめていくために何が必要かを明らかにすること。 | |
| (4) 学校づくりにおけるPTA、教職員組合、行政の役割をどうとらえ、その役割を発揮していくために何が必要かを明らかにすること。 | |
| (5) 政治が教育に大きく介入する情勢の下、「日の丸・君が代通知」「情報提供制度」などの教職員と学校を上から縛る政策や、「教職員評価制度」「査定昇給制度」など教職員への管理統制が進められる中、これからの学校づくりの課題を明らかにすること。 | |
| (6) 地域の衰退と「子どもの貧困」が進む中、福祉的支援がある学校づくりの視点を明らかにすること | |
第十七分科会 地域における子育て・学習運動
研究課題
| (1) 学校・地域をめぐる新たな動き | |
| ① 新自由主義(市場原理)に基づく教育体制の再編、効率主義の強化と格差の拡大(学校教育法、社会教育法の改定など) |
|
| ② 市町村合併と学校統廃合による教育施設の格差拡大 |
|
| ③ 学校教育における学力と評価「地域の教育力」の問い直し |
|
| (2) 地域における子育ての共同をどう広げるか | |
| ① 子育てについての親たちの悩み | |
| ② 子育てと学校教育の接点をどうつくるか | |
| ③ 地域における子育てネットワークをどう広げるか | |
| ④ 地域における子育ての共同と公的支援 | |
第十八分科会 地域と学校の文化・スポーツ活動
研究課題
| (1) 政治や経済の動きが、文化・スポーツ活動にどのような影響を与えているのか。また、退廃文化の中の子どもたちの現状はどのようになっているのか。 | |
| (2) 地域における文化・スポーツ活動をどのように進めたか(演劇・合唱・読書・図書館・読み聞かせ・民族芸能・スポーツサークル・学童保育・地域の伝統行事など)。 |
|
| (3) 学校における文化的・体育的活動をどのように進めたか(学校行事・生徒会行事・部活動・学校図書館・読書活動など)。 | |
| (4) 地域の文化行事やスポーツ少年団の現状はどのようになっているのか。 | |
第十九分科会 国民のための大学づくり
研究課題
| (1) 高大接続と大学改革の動向、それらが教育に及ぼす影響を明らかにする | |
| ① 高校教育と高校生の変化、大学教育への影響 | |
| ② 大学入試制度改革の動向(「到達度テスト」、センター試験・個別試験の改革、受験産業の影響) | |
| ③ 安倍政権の下、グローバル企業の要求と経済政策への従属を強める大学政策の動向 | |
| ④ 目標・評価と経営改革を通じた統制(「ガバナンス改革」)は、現場に何をもたらしているか | |
| ⑤ 教員養成・研修政策(教員養成・資格制度、免許更新制、教職大学院)の動向と問題点を解明する | |
| (2) 国民のための大学創造のとりくみ、実践的課題 | |
| ① 科学者と大学の社会的責任―研究不正、東日本大震災・福島第一原発事故の教訓 | |
| ② 誰もが学ぶことのできる高等教育の創造(奨学金・私学助成等の拡充、地域社会との連携) | |
| ③ 望ましい高大接続のあり方の探究(大学との関係を視野に入れた高校の学習・進路指導、高大連携) | |
| ④ 学生・教職員協働による研究・教育の創造 |
|
| ⑤ 学生の進路と社会的権利の保障 | |
| ⑥ 教職員の賃金、健康、労働条件を守るとりくみ |
|
第二十分科会 障害児・障害者の教育と福祉
研究課題
| (1) 小学校・中学校における特別支援教育の実践と課題 | |
| ① 通常学校における特別な支援や配慮の必要な子どもの教育の現状と課題 | |
| ② 通級指導教室の教育の現状と課題 |
|
| ③ 障害児学級の役割と現状と課題 | |
| (2) 障害児学校における教育実践と課題 | |
| ① 乳幼児期から学齢期までの相談・保育・教育・福祉の現状と課題 | |
| ② 訪問教育、医療的ケア、重度・重複障害児の教育の現状と課題 | |
| ③ 寄宿舎教育の役割と教育実践 | |
| ④ 「特別支援教育」の諸問題 | |
| (3) 青年期における特別な支援や配慮の必要な子どもの教育および就労・社会参加に関る現状と課題 |
|
| ① 高等養護学校の教育実践、進路保障、専攻科の課題 | |
| ② 通常高等学校における特別な支援や配慮の必要な子どもの教育の現状と課題 |
|
| ③ 寄宿舎教育の役割と教育実践 | |
| ④ 自立支援法の問題点と自立を可能とする生活保障の問題 | |
| ⑤ 卒業後の新たなとりくみの実践と課題 | |
| *一日目は「障害者虐待防止法と地域づくり・学校づくり(仮)」でシンポジウムを行います。 |
|
第二十一分科会 環境・公害と教育
研究課題
地域における自然・環境問題、学校・地域における自然保護教育・環境教育をみつめ、課題や問題点を科学的・総合的にとらえ、それに基づいて我々が何をなすべきかを問い、明らかにします。
| (1) 地域の自然・環境問題について、自然保護教育がどう行われ、子どもたちや地域住民にどう受け止められているのか、それぞれのとりくみついて交流し、課題を明らかにしましょう。生物多様性、外来種・生態系、希少種、自然の豊かさ、自然体験などをキーワードに討議を深めましょう。 |
| (2) 東日本大震災から三年半以上経過しました。今年は、局所的豪雨による土砂崩れで大きな被害が発生しています。災害→被災→復興と全国のあちこちで虚しい循環が繰り返されているように見受けられます。自然環境としなやかに共生しつつ地震や津波、豪雨などによる被害をいかにして軽減するかについて考えましょう。 |
| (3) 福島第一原発事故から三年半余り、事態は現在も全く収束しておらず、我々に大きな問題を投げかけ続けています。また、内部被曝による影響ではないかと疑われる事象も報告され始めています。深刻化する汚染水問題をどうするのか、原発の安定的な収束をどう行うのか、放射能汚染にどう対処するのか、人類は原発と共存できるのか、原発に替わるエネルギーをどうするのか、これらの問題に正面から向き合い、議論しましょう。 |
| (4) 地球温暖化による異常現象がいよいよ具体的な形で表れてきたのか、そのほか熱帯林の減少などグローバルな環境問題は、学校・地域でどう取り上げられ実践されているのか、現状と課題を考えましょう。 |
| (5) 運動や教育実践の中で、教師・研究者・地域住民の横の連携、ネットワークの現状は、どのようになっているのか。連携を深める仕組み作りや課題を明らかにしましょう。 |
第二十二分科会 平和・憲法、人権・民族と教育
研究課題
《平和・憲法》
昨年十一月の「特定秘密保護法案の可決」、今夏七月の「集団的自衛権」の閣議決定と、「戦争のできる国づくり」が始まっています。この流れに私たちはどう立ち向かうのか。しっかりとした理論と状況判断が求められています。 また戦後六十九年をむかえ、私たちはこれまでの日本が作り上げてきた「文化としての平和」を構築し世界に広める時期を迎えています。実践と理論を学びあいましょう。
| (1) 「憲法改正を諦めた」現政権の狙いは何なのか。そしてそれに対する私たちの理論立てをどう進めていくのか。 |
| (2) 同時に憲法を守る運動をどのように展開していくのか。 |
| (3) 「文化としての平和」を地域や教育現場でどのように展開していくのか |
《人権・民族と教育》
| (1) アイヌ民族その他の民族的少数者が日本社会の中で直面している課題を明らかにし、その克服のすじみちを考えます。 | |
| (2) アイヌ民族その他の民族的少数者の歴史と現状にかかわる課題を、教育実践としてどう取りあげたか、その成果を交流します。 | |
| (3) 社会の中で、少数者であるために、差別・無視・排除など様々な「人権」侵害に遭遇している人々の例について理解を深め、「人権」感覚の深化と、つながり合う行動への契機を探ります。 | |
第二十三分科会 子ども・青年の発達と教育
研究課題
| (1) 子ども・青年の現状、家庭・地域・学校の現状を具体的に話し合い、交流・理解していく | |
| ① 子どもの声・文章を持ち寄り、検討する。 | |
| ② 具体的事例から、分析、共有を図る。 | |
| (2) 子ども・青年の生活と発達の保障・援助という観点からの報告と検討を総合的に行う。 | |
| ① 実践報告から、その分析・共有の中で、現代日本社会における子ども・青年の生活と発達について考える。 | |
| ② 学校以外での実践や活動の報告を受け、発達援助のあり方を総合的に検討する。 |
|
| (3) 子ども・青年の発達援助に関わる方々の困難と希望を話し合う。。 |
|
| ① 教師だけでなく、幅広い発達援助職の方々とのこうりゅうと対話を通して連携・共同のあり方を深める。。 |
|
| ② 子ども・青年の発達と教育分科会の価値の再認識を図る。。 |
|
第二十四分科会 不登校・登校拒否・高校中退
研究課題
| (1) 不登校・登校拒否・高校中退・ひきこもりなどの現状について | |
| ① 学校、地域の実態交流 | |
| ② 「経済格差」「学校の序列化」が子どもにもたらすこと | |
| (2) 不登校・登校拒否・高校中退・ひきこもりなどに、どのようにとりくんでいるか | |
| ① 教育機関の柔軟な対応 | |
| ② 当事者、保護者のこれからの進路などについて | |
| ③ 支援機関のとりくみを交流する | |
| ③ 子ども、青年期以降の実態ととりくみについて | |
| (3) 私たちができることは何か | |
| ① 公的支援の充実を求める活動 | |
| ② 家族支援と地域社会の理解を広める | |