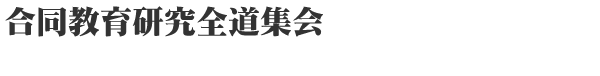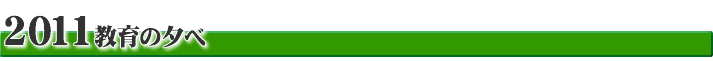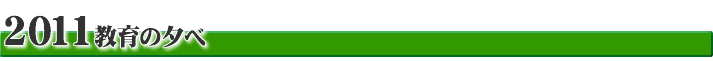
開会挨拶

|
|
|
北海道大学の姉崎です。
みなさんご存知のように、この合同教育研究集会はいろいろな方たちの力で成り立っているのですが、小学校、中学校、高校の先生方、私学、そしてさまざまな市民団体の方々が参加されておりますが、大学もそのひとつの役割を担っております。私はその大学の教職員組合の全大教北海道の役員をしておりまして、この研究集会の実行委員会の代表委員もつとめておりますことから、ごあいさつをさせていただいております。
さて、これから記念講演を行われる千葉大学の片岡先生からは、「危機を希望へ」というタイトルでお話しを頂戴することになっています。
ある意味「3・11」の東日本大震災は、希望を危機のなかに陥れました。そして、多くの人が、いまこの危機を希望へと転ずるべく、力を尽くされている、そのさなかに私たちは今日の集会を迎えています。
今年は2001年の「9・11」から数えても10年という節目の年です。「9・11」そして「3・11」は、一方の「9・11」は国際政治のさまざまな葛藤のなかで起きたという点において、そして、もう一つの東日本大震災「3・11」は地震・津波という天災に福島の事故が加わり、人類が持っている科学・技術や開発への信頼を打ち壊し、大きな犠牲をもたらし、生きる希望を奪い去ったという点において、いずれの出来事も大きな転換を人間に迫っているのではないかと思います。
現代社会は、大きな危機を内包しているという意味で「危機社会」とか「危険社会」とか、あるいはあらゆる価値が転換を迫られているという意味で「液状化社会」などとも呼ばます。
しかし、この危機は希望へ転じることもできたのではないか、危機は英語でクライシスですが、病気でもそれがある大きなクリティカルポイントを超えると、恢復過程に入ると言われるように、いま私たちの目の前にある危機を希望に転じていくことが課題なのではないでしょうか。
私たちは二つの人類史的な大事件を単なる事件にとどめず、危機を希望に転じ、安全・安心な社会に組み替えていることができないか、と問いたいのです。
私は、先ほどまでの高校生の演劇も、「危機の中で希望を考える」という今の私たちの課題を考える手がかりを与えるものであったように感じました。「はるにれ」を一つの定点にし、描かれていたのは、まさに希望だったのではないでしょうか?かつてブレヒトは「演劇は世界を変えることができるか」と問いました。教育学においてもフレイレという人は「希望の教育学」というものを書きましたけれども、まさにそれが問われています。
私たちが直面している現実は生やさしい状況とは言えませんが、このあとの講演、そして明日の分科会を通じて、現在の危機を希望に転じる二日間になればと願っております。
今日からはじまった分科会には、私の大学のゼミの学生たちも参加していましたが、大学のゼミの際より立派な発表をしていたように思います。ここにも希望を感じた次第です。
二日間、どうぞよろしくお願いいたします。
|