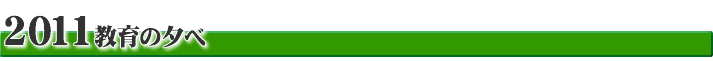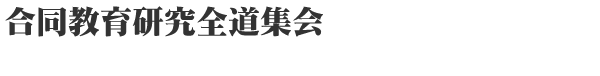
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|
|||
|
|||||
記念講演
危機を希望に ~大震災・原発人災を、子ども・青年と生きる~
片岡 洋子氏

集会1日目「教育の夕べ」で記念講演に立った片岡洋子さんは、生活綴方研究を通した「発達と教育」を原点とし、生活指導の研究家として、揺れながら成長していく子どもたちのなかから、人間らしく成長したいとの願いや現代社会がつきつけている生きづらさの本質をあたたかな視点で見いだしていきます。その著作や発言に多くの教師や親が励まされてきました。
今回の集会での演題は、「危機を希望に~大震災・原発人災を、子ども・青年と生きる~」。
〝原発人災〟が問い、求めている教育の課題と「希望」を自らの生育史に重ね合わせ、熱く語りかけてくる講演は、全道からの参加者を励ましました。

美しいふるさとが…
片岡さんのふるさとは東京電力福島第1原発から「10キロ圏内」の福島県富岡町。しかし、「ツツジが満開になると常磐線を走る特急列車も徐行する」美しいふるさとのこのまちには、もはや立ち入ることはできません。
「何も分かっていなかった」
「高校卒業後は年に何度か帰る程度だった自分でも、18歳まで過ごしたふるさとを失った喪失感は大きい」「でも、もっと大きな衝撃は、この〝事故〟が起こってしまってから、自分は何も知らなかったことに気づいたショック」と語った片岡さん。「心情的には原発は不安だった。でも何もわかっていなかった」。高校までを石巻で過ごした作家の辺見庸さんは、津波と火災におそわれた石巻の惨状に「3月11日までの言葉では語れない」と書いています。今の日本の現状は、〝戦中・戦後〟と変わらないのでは?と問います。
「これが正しいと説明されてきたものが根本から覆り、問われている」。しかも、「安全神話を広げるため、子どもたちも動員されていた」現実と教育の責任をするどく指摘しました。
授業づくり
「今、自分にできることは何か」を考え、ご自身の大学の「授業研究(授業開発研究)」を、「原子力を考える」という統一テーマで行うと提案しました。「怖すぎて、向き合えない」との学生の声もありましたが、〝安全神話〟が蔓延している現状を変えていくためには、「何となく不安、何となく知ってるつもり」から「何も知らなかった」「難しい」「でも知りたい」へと進むような「授業づくり」こそが求められています。「ヒロシマ」「ナガサキ」「フクシマ」を核の問題としてつなぎ合わせ考えていくことの大切さを訴えました。
希望
お互いを思いやる避難所で成長した子どもたち、災害のなかで「不自由」だけど輝いていた学校の存在は、新学習指導要領が本格実施され、「学力低下」や「規範意識」ばかりが問題視される「普通の学校」の異常さを浮き立たせます。福島県ではやっと「反原発」の声もおおっぴらにあげられるようになり、母親たちの声が国や県を動かしはじめました。アメリカウォール街から始まった「99%のための政治」を求める運動にも通じる動きこそが、危機を希望へつなぐかけはしとなると熱く訴えました。

●参加者感想
〇原発教育のあり方について、もう一度考え直します。
〇政府が「何か隠しているな」と思った人はたくさんいたと思います。誰かと原発のことを話すだけでも何かは変わるかもしれない。自分のことばかりでいっぱいになっている毎日ですが「何か」はできるかもしれないと感じました。
〇「情報を批判的に読むこと」「平和学習のあり方」本当に考える機会になりました。
〇3月まで福島県いわき市で教師をしていました。偶然にも4月から北海道に来ることになっていたので私は3月中の福島の様子しかわかりませんが、それでも、3・11以降のことは忘れられません。(中略)今日は本当にありがとうございました。
〇最後の平和教育への「投げかけ」がぐっときました。
〇いろいろ考えさせられました。「当たり前」と思っていることを、もう一度見直してみる、考えてみることが必要だと思いました。
〇「まるで何もわかっていなかった」戦中と同じよう。知らないうちに情報を操作されているのかもしれない。正しいことを子どもたちに伝えなければならないと感じました。
〇「問い直す」ということ改めて考える機会を持てました。
〇お話を聞きながら、3・11があらためて1人1人の生き方を問い直す契機になっていることを強く感じ、ご自分を生い立ちにさかのぼってさらけ出しながらの報告にうたれました。体験や肉感性に裏づけられた新しい個人と社会の論理を構築することを通して、〈危機から希望へ〉の展望がひらけるのかなという気持になっています。
〇福島とつながりが深い方だとは知りませんでした。3.11に対する素直な思いと、教員を育てる大学で何ができるかを語りながら、私たち一人一人にも、子どもたちへの向き合い方を問題提起していただけたと思っています。